新幹線の「顔」を作り出す人たち 【テクノえっせい】
2007年10月01日
いまや新幹線は、まさに日常の足です。特別なことを考えずに乗っているのですが、あの複雑で特異な形状の先頭車両を誰が、どこで、どのようにして作っているのか考えたことがありますか。
7月1日に新型の車両N700系の運行が始まりました。現在の技術と将来の可能性を結集した最高水準の列車で、減速せずにカーブを時速270kmで走り抜けられるといいます。
スピードだけではなく、これまでは車両の前後の扉に近い席にしかなかった100Vの電源コンセントが、お客さんの要望に応え、普通車の窓側の席すべてに用意され、パソコンが使えるようになったのです。こういう点でも世界に誇る鉄道になってほしいものです。
☆特異な先頭車両
ご存知のとおり、新幹線は東京オリンピックの年、つまり昭和39年の10月1日に営業を開始しました。したがって今年は43年目になりますが、先頭車両のあの特異な姿は変わっていません。
はじめて世に現れたとき、誰しも思わず目を見張ったものです。なぜならそれまでの鉄道車両といえばだいたい四角い箱型が基本で、流線型だといっても、せいぜい正面が少し丸みを帯びている程度だったからです。
最初の新幹線は、鼻先が丸く突き出たダンゴ鼻。しかもその鼻先は色の違う菅笠風で愛嬌がありました。その斬新なデザインに、大人も子どもも引きつけられたものです。
昭和60年からは100系、平成4年からアルミ製の300系となり「のぞみ」が誕生しましたが、とがった先頭車両の顔はますます伸び、地面を舐めるような姿になりました。
平成9年にデビューし、時速300kmを達成した500系や平成11年の700系でも傾向は変わらず、「カモノハシのくちばし」を思わせる形になりました。今回のN700系でも同じで、やはり鼻先は長いのです。
先頭が長くなっているのは、空気を切り裂くときの力を考慮するからで、省エネにも、また騒音の低減対策にも重要なのです。またトンネルの入り口での衝撃力や、すれ違いの際の風圧の問題もあります。とにかく先頭車両は、空気力学を縦横に使った設計になっているのです。
終戦後、わが国は航空機の開発が禁止されました。それでこの分野の優秀な人材は、新幹線の開発に活躍の場を見いだしたといいます。この繋がりからすれば、新幹線の先頭部分が大型航空機の姿に似てくるのも理解できます。
―1―
☆どうやって作るのか
今年の第2回ものづくり日本大賞に応募してこられた㈱山下工業所の山下清登さんをはじめとするグループの書類をみて目を見張ってしまいました。この新幹線先頭部分を作って40数年、納入したのは330台とあります。
日本が誇る新幹線といいながら、その特異な先頭車両を誰が何処で作っているのか考えたこともなかったという自らの甘さにたじろぎ、恥ずかしい思いになったのです。
形については空気力学的に決められたものでしょうから、とやかくいうことはできません。とにかく作ることなのです。数量が多い自動車なら金型を作りプレス加工となるでしょう。あるいは部分ごとにブロックから削りだす方法も考えられますが、引き合わないでしょう。
とにかく数が多くないのです。先頭車両は1列車あたり前後の2台しかありません。40数年で平均したら年に10台程度で、しかも大型で複雑なのです。大量に作ればどんどん捌けるという代物ではありません。それにコスト低減と納期短縮の要請もあります。
山下さんは、当時いろいろな方法を考えてみたといいます。その結果、最後にたどり着いたのは、自らが自動車修理工場で身につけた伝統的な打ち出し加工法だったのです。
これは自動車のへこみを直して貰うときの板金加工の手法なのですが、実は広島の伝統工芸品である「銅虫(銅蟲)」の製造法でもあります。銅虫は浅野候がお抱え職人清氏に創案させて命名したものといわれ、銅版を叩き出して火鉢や花瓶、皿などを作っていくのです。
☆技能と感性に裏打ちされて
訪ねてみたら、典型的な中小企業の工場でした。日立製作所笠戸工場の隣です。日立製作所はわが国で新幹線車両を作っている車両会社の一つで、作った車両の先端部分は日立製作所に納められているといいます。そこまでは知りませんでした。
初めのころ新幹線は、鋼板で作られていました。全体を部分に分けて素材を切り出し、加熱して型にあてがい、ハンマーで打ちながら曲面を作り出していったといいます。鋼板なので重いし、加熱して叩くのですから暑くて決して楽な作業ではありません。騒音も大変なものだったと想像されます。
車両の軽量化の要請から、素材はアルミニウム合金に変わりましたので、現在は加熱の必要がありません。部分に分けた板材は手に持てる程度の大きさです。手持ちハンマーや自動ハンマーで微妙に曲面を作り出しながら、板を手で細かく動かし、そして叩くという作業を繰り返していきます。曲げすぎてはなりません。
この方法では複雑な曲面を高精度に仕上げることが可能なために、最後に組み合わせて溶接するときに狂いがなく、歪み取りの作業をする必要がないのだといいます。
とにかく仕上がりは美的でなければならず、作業者の技能と感性に大きく依存していることがよく分かります。それだけにこの技術を体で覚えるのには、軽く10年はかかるといいます。グループに年齢幅を持たせて、技術の継承に努めているのだという説明には、納得させられるものがありました。
わが国として、失いたくないものづくり技術の一つです。このたび平成19年度の第2回ものづくり日本大賞では、経済産業大臣賞特別賞に輝いたのであります。(広島工業大学 中山勝矢名誉教授)
―2―
- [ 出典 ]
- 広報誌『METI CHUGOKU』 2007年10月1日 P.1 P.2 / 経済産業省 中国経済産業局

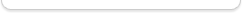
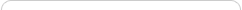
 経済産業省選定
経済産業省選定 経済産業省 令和元年度 事業継続力強化計画認定
経済産業省 令和元年度 事業継続力強化計画認定 経済産業省選定
経済産業省選定 第2回ものづくり日本大賞経済産業大臣特別賞受賞
第2回ものづくり日本大賞経済産業大臣特別賞受賞 KES・環境マネジメントシステム・スタンダード登録事業所
KES・環境マネジメントシステム・スタンダード登録事業所